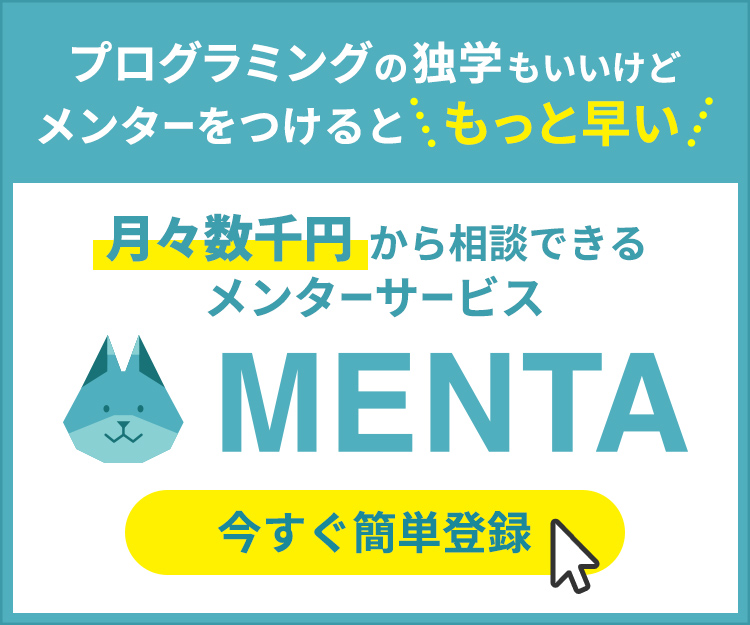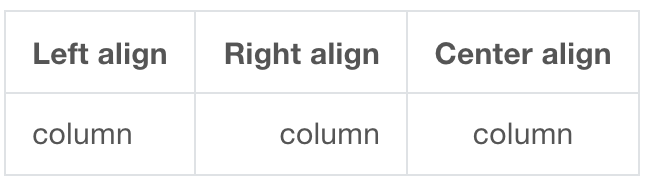新規事業おじさんのつぶやき Vol.42 競争領域と非競争領域
何年も前から始まっていることなので、ニュースにもなりませんが、ビール、日用品メーカーなどが共同配送を始めた時は結構なニュースになりました。
それまで、各社が物流、配送を独自に行っていたものを相乗りにして、効率向上、単位コストの低減を図る取り組みであることは皆さんご存知かと思います。
一方、アマゾン、楽天、ヨドバシカメラ、アスクル....といった企業群での物流、配送で相乗りするという話は聞いたことがありません。
この違いは何から来るのでしょうか。
前者の企業群にとっての競争領域は自社の商品そのものであって、物流、配送は補助機能という位置づけですね。ですから、物流、配送は非競争領域です。
後者の企業群にとってはどうでしょうか。物流、配送の品質で競争している企業群ですよね。物流、配送は競争領域です。
新規事業立ち上げの際に悩むことの一つに、特定企業のみに縛られると、規模が限定されて、採算化のロードマップを描きづらくなるというものがあります。
一方、やっとの思いで見つけた最初のパートナー企業には思い入れもあります。とにかく、その会社向けに製品、サービスを立ち上げて、早く、成果を示したい。痛いほどわかります。
ですが、ここで、パートナー企業の競合へのアクセスをブロックされると、事業がスケールしません。
ここで、競争領域と非競争領域の考え方を使うというのが一つの方法にならないでしょうか。
製品、サービスによって提供する機能、利便性がパートナー企業にとっての非競争領域であれば、それを自分たちの新規事業にアウトソーシングするという考え方を持ってもらうという考え方です。
同時に、自分たちにアウトソーシングしてもらう製品、サービスを用いて、パートナー企業には自身の競争領域での競争力向上に役立ててもらうことも考えるのです。
こうすることで、製品、サービスの1階部分は全体共通でスケールして、採算ラインに少しでも早く到達する。
2階部分は各社ごとにカスタマイズして、パートナーごとに特徴を出してもらう。
では、本当にやるのはどうするの?
それ? 別の場で個別にお話することでしょう。
(本稿は2023年に公開した記事の再掲です。)