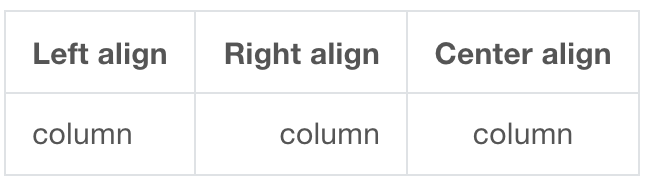書評:前置詞byの意味を知っているとは何を知っていることなのか
以前にnoteにて執筆した、『前置詞byの意味を知っているとは何を知っていることなのか』という本への書評です。前置詞というものを理解する上で非常に重要な知見がまとめられた、希有かつ有益な本であると思います。
いわゆる前置詞については、理解について複数のフェーズがあるように思います。
まず、「日本語で対応させてはいけない」と考えるフェーズ。これは、例えばofという前置詞を「〜の」という助詞と対応させることに無理があると気付くフェーズです。そして次に、「イメージで覚える」フェーズ。atは点、onは面、inは内、といったように、言葉ではなく概念やイメージで覚えるというフェーズです。
しかし本書では、それを更に一歩進めて、『現実でどう扱われているか』を考えます。本書を読むことで、イメージで覚えるフェーズでは捉えきれない用法というものが、少なくともbyを見るだけでも多く確認できることが明らかになります。これは他の前置詞にも言えることでしょう。
もちろん、本書を読むことでbyという単語に対する理解が深まることは言うまでもありません。しかしそれ以上に重要なのは、そこから前置詞というものに対する理解のアプローチを転換させることにあるのです。
前置詞byの意味を知っているとは何を知っていることなのか:https://amzn.to/2Ft7Qks
・・・以下、noteからの引用です・・・
この本は、英語学習者にとっての絶望の書でもあり、福音書でもある。それが、読んだ直後の僕の印象だ。
本書は、前置詞byを使いこなせるようになるための本ではない。前置詞byの用法を見ていくことで、一般的に言われている『前置詞をイメージで覚える』ことや、『前置詞に広く共通するイメージを持たせて覚える』ことに警鐘を鳴らしているように思う。それが、『多義論から多使用論へ』という副題が意味しているところだ。
ここで言われる多義論というのは、前置詞というものを多義的に扱うことについて触れている。例えばbyなら、『〜の傍に』や『〜によって』、『(数の差を示して)〜だけ』といったような意味を持つというように考えられるのが一般的で、辞書にもそのように書かれているが、実際にはこのような多義語としての考え方ではカバーできない用法がたくさんあるというのが本書の趣旨だ。
仮にbyが、『〜の傍に』や『〜によって』といった多義的意味を持つ言葉だとすれば、そこから逆算して『どういうときにbyを使うべきか』ということが分かるはずだ。しかし実際には、そこから逆算しても辿り着けないbyの用法が数多くある。そうなると、byの個々の用法を見ていって、それを個別に学習しなければ、byを使いこなしたことにはならないのだ。これが多使用論の意味するところである。
それは『根源的意味や共通のイメージでbyについて学び、それを敷衍したり演繹したりすることでbyという言葉を使用することには限界がある』ということだ。いわゆるネイティブは、このbyの使い方を当たり前の感覚として身につけている。byに特定の意味があるからそのような言い方をするのではなく、byの使い方とはそういうものであるということを理解しているのだ。僕たちは、それを外から見てbyの意味を帰納しようとしているに過ぎない。
だがその帰納法から得られるイメージは、ネイティブが持っているbyへのイメージとは違うものだ。僕たちは、ネイティブが持つbyへのイメージを帰納することはできないし、したがって、ネイティブのbyの使い方を100%理解することは難しいと言えるだろう。それは、『ネイティブ並みの完璧な英語』という幻想を目標とする人たちにとっては、絶望を告げる予言にも聞こえるかもしれない。
だからこそbyという言葉を使いこなすには、個々の用法を学習し、愚直なほどに真っ直ぐに勉強していかなければいけないということになる。だがこれは逆に考えれば、『個々の例からbyという言葉の使い方を覚えていけば、その経験値によって、適切な状況においてbyという言葉を正しく選択できるようになる』ということを示しているのでもある。これは、これまで多くの学習者がbyという前置詞に対して関連付けようとしていた帰納的イメージに納得できていなかった人たちにとっては救済になるはずだ。ただ愚直に学び続ければ良いのだから。
本書は、その多義論からの帰納の限界を探りつつ、実際の使用の中にどういった例外が存在するかということを考えつつ、byというものが現実世界でどう使われているのかを考えていく。本書を読み終わった頃には、byという前置詞が実際の使用としてどういった意味合いや機能を持つのか、より学びを深められているに違いない。
そしてもちろん、それはby以外の前置詞についても言うことができるだろう。この本は、前置詞というものを学び、考える上で、どういったパラダイムが重要になるかを示してくれる画期的な本である。