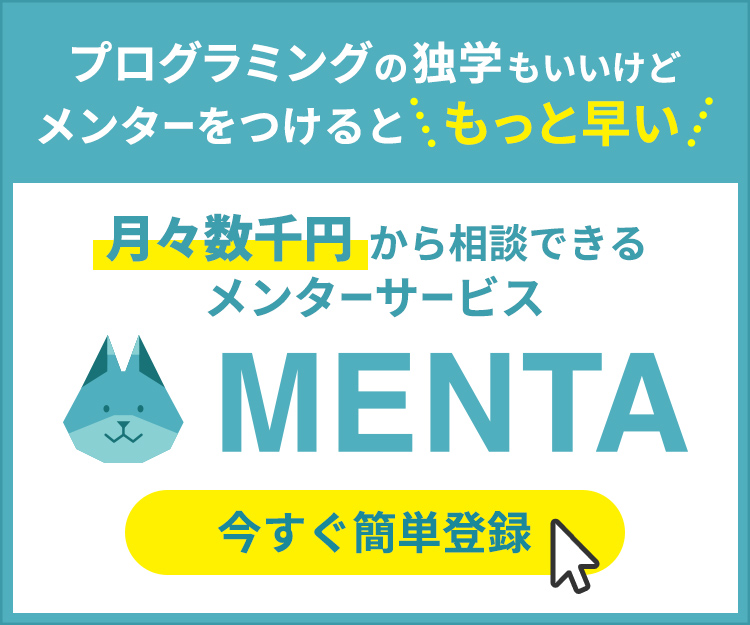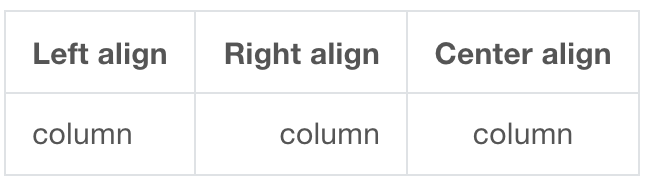新規事業おじさんのつぶやき Vol.78 3種類の人材をかけ合わせたチームが必要
以下は、本の紹介記事からの引用ですが、「ビジネス(B)・テクノロジー(T)・クリエーティブ(C)という3種類の人材をかけ合わせた最大5人程度のチーム」というのが確かにその通りだと思うポイントです。
ところが、1社でこの3種類の人材が揃ったチームを組むことは可能なのか?
これは結構大きな問題だと思いますし、私自身も苦悩と葛藤を抱えるということをずっとしてきました。
たとえば、メーカーの場合ではテクノロジー(T)の人が技術軸で新規事業を起こそうとするケースが大半でしょう。では、社内にビジネス(B)人材がチームに加わってくれるのか。ここでつっかかるケースは多くありますし、多く見てきました。
たとえば、商社ではどうでしょうか。ビジネス(B)の人が新規事業の企画を考え、立ち上げようとされるというのが、ほぼ100%ではないでしょうか。したがって、テクノロジー(T)人材を求めて、メーカーとのアライアンスを構築するといったことでカバーするというケースが多いように見受けられます。
さて、クリエーティブ(C)人材はどこにいるのでしょうか。JTC企業の中には、失礼ながら、なかなかいないのではないでしょうか。これについては、私自身がクリエーティブ(C)に決して強い人ではないので、掘り下げが必要なのですが、ビジネス(B)人材であれ、テクノロジー(T)人材であれ、その新規事業に対する深い思い入れと執念深さを持っていれば、たゆまぬ努力を通じて、クリエーティブ(C)を助けてくれる人々とのネットワークを築き、そこからの学びを組み込んで行けるものだと思っています。
その本は井上一鷹『異能の掛け算』(ニューズピックス)。副題には「新規事業のサイエンス」とある。
本書はその経験で培ったノウハウを一冊にまとめたものだ。全体はチーム論と方法論に分かれており、本のタイトルにもなっている「異能の掛け算」とはチーム論の中核になる考え方をさす。ビジネス(B)・テクノロジー(T)・クリエーティブ(C)という3種類の人材をかけ合わせた最大5人程度のチームを組成することが理想の価値創造をめざす大前提となる。
(本稿は2023年に投稿したものの再掲です。)