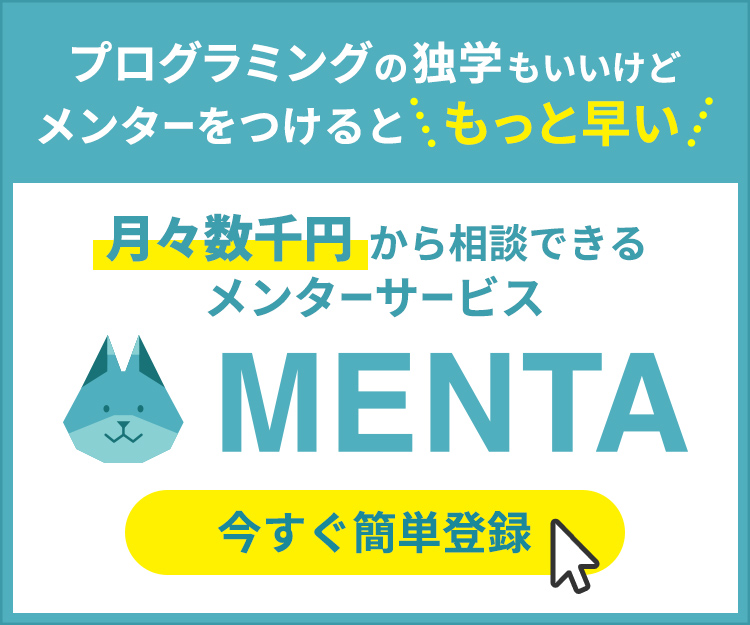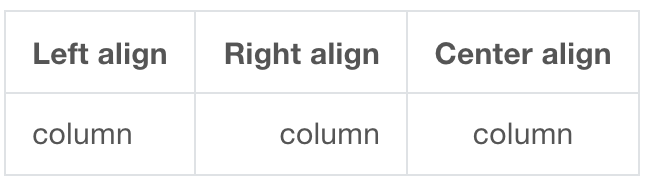【私がコーチとして大切にしていること】デザインを教えるときに重要な"思考力の鍛え方"
はじめに
デザインを学ぶ際、多くの人は「ツールの使い方」や「レイアウトの技術」に目を向けがちです。しかし、本当に価値のあるデザインを生み出すには、「思考力」を鍛えることが不可欠です。デザインの本質は、「見た目を整えること」ではなく、「問題を解決すること」。そのため、教育者としてデザインを教える際には、単なるスキル習得ではなく、思考力を鍛える指導を心がけています。
1. デザインにおける「思考力」とは?
デザインに必要な思考力とは、単なるアイデア発想ではなく、ロジカルに物事を考え、クライアントやユーザーの課題を解決する力です。これには、以下の3つの思考が含まれます。
1.1 クリティカル・シンキング(批判的思考)
物事を鵜呑みにせず、論理的に分析する力。
「このデザインはなぜ良いのか?」「なぜこの配色なのか?」と問い続ける習慣。
1.2 デザイン・シンキング(デザイン思考)
ユーザー視点で課題を発見し、解決策を考える力。
例:「ユーザーが使いやすいWebデザインとは?」
1.3 コンセプチュアル・シンキング(概念的思考)
抽象的なアイデアを具体的なデザインに落とし込む力。
例:「このブランドの価値観をどうビジュアルで表現するか?」
2. 思考力を鍛えるための教育アプローチ
思考力を鍛えるためには、受講生に「考える習慣」を身につけさせることが重要です。そのための具体的な方法を紹介します。
2.1 「なぜ?」を問い続ける指導
デザインの授業で、以下のような質問を投げかけることで、受講生に論理的な思考を促します。
例:ロゴデザインの講義で
「なぜこのフォントを選んだの?」
「この配色はブランドの価値をどう表現している?」
「このデザインはターゲットに適している?」
ポイント
回答が曖昧な場合はさらに深掘りして問いかける。
「感覚」ではなく「理由」を言語化させる。
2.2 ケーススタディを活用する
実際のデザイン事例を分析することで、論理的思考を鍛えます。
実践方法
優れたデザイン事例を提示し、「なぜこのデザインが成功しているのか?」を議論する。
失敗したデザイン事例を提示し、「どう改善できるか?」を考えさせる。
過去の自分のデザインを振り返り、改善ポイントを洗い出す。
メリット
良いデザイン・悪いデザインの違いを理解できる。
クライアントワークでの提案力が向上する。
2.3 「制約」を設けたデザイン課題を出す
自由にデザインを作らせるだけでは、思考力は鍛えられません。制約のある課題を出すことで、創造的な問題解決力を養います。
例:制約付きデザイン課題
「2色のみでブランドロゴをデザインする」
「5文字以内のキャッチコピーで訴求力のある広告を作る」
「1ページのLPで商品の魅力を伝えるデザインを作る」
ポイント
限られたリソースの中で最適な解決策を考えさせる。
クライアントワークでの現実的な課題解決力につながる。
3. デザイン教育における「考えさせるコーチング」
思考力を鍛えるには、「答えを教える」のではなく、「考えさせる」ことが重要です。
3.1 ソクラティック・メソッド(対話型教育法)
受講生が自ら答えを導き出せるように、質問を通じて思考を深める手法です。
実践例
受講生がデザインを提出したら、いきなりフィードバックをせず、「なぜこのレイアウトにしたの?」と問いかける。
「このデザインの目的は?」「他にどんな選択肢があった?」と考えさせる。
3.2 フィードバックのステップ
気づかせる:「この部分、意図は何?」
比較させる:「AとB、どちらがより効果的?」
選択させる:「どの方向性で進めるのがベスト?」
4. 教育者としての権威性を強化するには?
4.1 体系的なメソッドを確立する
受講生に「この人から学びたい」と思わせるためには、独自の教育メソッドを確立することが重要です。
例:思考力を鍛えるためのメソッド
「3ステップロジカルデザイン思考法」
「デザイン改善チェックリスト」
「クライアントワークのためのヒアリングシート」
まとめ
デザインを教える際に重要なのは、「ツールの使い方」ではなく、「考える力」を鍛えることです。思考力を高める指導をすることで、
✅ 受講生のデザインスキルが飛躍的に向上する
✅ クライアントワークで提案力が身につく
✅ 教育者としての権威性が高まる
デザイン教育の本質は、単なるスキルの伝授ではなく、「思考力を鍛え、クリエイティブな問題解決ができるデザイナーを育てること」です。これを意識しながら、より質の高い教育を提供していきます。