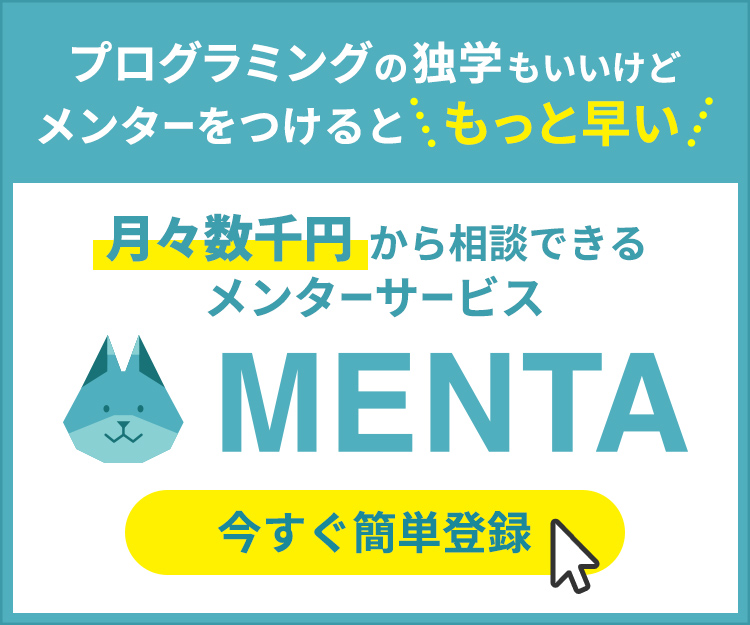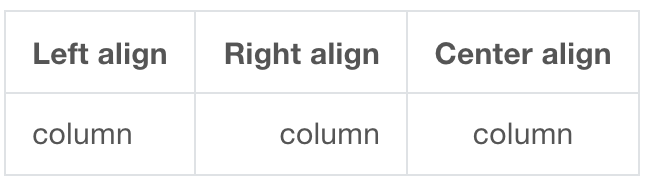新規事業おじさんのつぶやき Vol.79 半導体産業の歴史から学ぶ
本連載では、これまで、新規事業に固有の原理、考え方、経験知の共有を意識した内容を取り上げてきました。
それらに加えて、産業界を広く見渡すと、新規事業担当者にとって、多くの学びを与えてくれる事例があることに気づかされます。今回は、私自身も身を置いてきた業界である半導体産業の歴史から学ぶヒントをピックアップしたいと思います。
以下の記事から、いくつか、学びを与えてくれるくだりをピックアップしてみます。
>日本が半導体戦争に惨敗した真因ーーソフト開発軽視が致命傷に
https://36kr.jp/216461/
ソニーのラジオが大ヒットしたことで、川下の巨大な消費市場から収益を上げて技術開発のコストを下げ、さらなる技術の改良に生かすという、半導体企業にとっての成功の道筋が示された。ここでキーワードとなるのが「市場」だ。
屋台骨ともいえる産業の衰退は、産業界で繰り返し議論の的になり、常々思い返されてきた。西村吉雄氏は著書「電子立国は、なぜ凋落したか」の中で、日本企業は「製造方法」の研究には長けているが、「何を作るか」の判断がおろそかだったことを指摘している。
この新たなシステムのもと、付加価値の源泉は製造スキルやコストコントロールから、ソフトウエア開発のアーキテクチャや川下のアプリケーションへと移ってきたが、日本人はこの変化になじめなかった。
西村氏が語ったとおり、日本企業は優れた「ものづくり」の精神にあふれてはいたが、クアルコムやインテルにも、グーグルやアマゾンにもなれなかった。
日本人が半導体産業を振り返るときによく耳にするのが、「技術ではなく、市場で負けた」という言い訳だ。トップクラスの演算能力を持つチップを設計するのはもちろん容易なことではない。しかしその先に、チップをもとにソフトウエアを開発する企業や、それにお金を払う消費者がいることを忘れるべきではない。
これらのくだりを取り上げて、皆さんは何を感じ、思い浮かべられるでしょうか。
私は「それを使って、何をするのか?何を提供するのか?」が鍵であるということを再認識しました。
繰り返します。
これらのくだりを取り上げて、皆さんは何を感じ、思い浮かべられるでしょうか。
正解は一つではないはずです。皆さん、一人一人が感じ、思い浮かべたことからの学びもあるはずだと、私は思います。
(本稿は2023年に投稿したものの再掲です。)